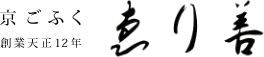京都の学生さんと見つめなおす”きものの愉しみ”
~箪笥に眠る物語(3)
こんにちは。
同志社大学社会学部1回生の松浦未空と申します。
京ごふくゑり善様にご協力頂き、「First Year Program in Kyoto」 にて
箪笥に眠る物語というプロジェクトを進めさせて頂いております。
前々回、前回の内容はいかがでしたでしょうか?
今回は戦争や阪神淡路大震災をめぐるエピソードを中心に書かせて頂きます。拙文ではございますが、最後までお読み頂けると幸いです。
まず、当プロジェクトのサポーターを務める木村さんのお母様のお話です。
木村さんのお母様は20代前半の頃、
ご友人の結婚式に出席するにあたり礼装として着用するために着物を購入されました。
大学卒業後働いて間もなかったため、ご自身が買うことのできる安価な着物でした。
成人式には無地の鴬色にわずかな刺繍が入った振り袖を購入し、
その振り袖を大変気に入ったため、無地の着物を選ばれました。
もともと母方のおばあさまは数枚着物を持っておられ、
家には着物をいれるための箪笥もあったようです。
しかし阪神淡路大震災の被災を受け、その後数回の引っ越しをすることになり、
残念ながらその着物はなくなってしまいました。
また、所有されていた着物の数枚は着ることがなく、
正しい管理が出来ていなかったため、茶色の斑点が出来てしまい、捨てることになってしまいました。
では、なぜこの着物は残っているのでしょうか?
それは、この着物は初めてご自身のお金で購入されたものだったため、
例え着ることがなくても手元に置いておきたいと思われたからです。
お母様は「今後はお直しをしてもう一度自分で着てみたい、そして娘にも受け継いでほしい。」とおっしゃっていました。
今回のインタビューをした木村さんのコメントです。
私はこのインタビューをするまで、
我が家にこのような着物、そしてそれにまつわる様々な想いがあることを知りませんでした。
しかし、この機会を受けて私は母の想い出が詰まったこの着物を受け継ぎたいと思いました。
特に、阪神淡路大震災に関連して着物を失うことになってしまったという話を受け、
大切な想いが詰まった着物がいつまでもあることが当たり前ではないと感じました。
着物は私にとって高級品であり、簡単に買うことができません。
しかし、当時の母も一生懸命働いて得たお金で買ったという話を聞き、
私も将来自分のお金で着物を買い、箪笥に眠らせるのではなく、
たくさん着ることを通じて想いの詰まったものにしたいと思いました。
一着だけ残っているところにその着物への思いの深さが分かりますね。
着物は高価なのでなかなか買うことは難しいですが、その分一着一着への思い出が詰まっています。
木村さんが受け継ぐことで、お母様の初めてご自身のお金で購入された嬉しさなど、様々な思い出が伝わるのも着物ならではだと感じました。
また、木村さんの「大切な想いが詰まった着物がいつまでもあることは当たり前ではない」という言葉が印象的でした。
災害や戦争などにより、大切に保管していてもやむなく手放さざるを得なくなることはあると思います。
現在受け継がれている着物を大切にしたいと強く思うと共に、着物が残っていなくてもそれにまつわる思い出は親から子へと受け継いでいけたらと感じました。
次はメンバーの阪本くんのお話です。
阪本くんのご実家ではひいおじいさまの代まで悉皆業をされていました。
悉皆業とは、着物の洗濯、アイロンがけ、染め直しや色抜き、染み抜きなどの様々な専門業者とお客様を仲介する仲介業者のことです。
昔は帯を作るだけで儲かりましたが、戦後には洗濯機で洗える着物ができたり、
洋服ブームで着物自体をみかけなくなったりと時代の変化がありました。
それに伴い、阪本くんのご実家も仕事を続けるかどうかの選択を迫られました。
おじいさまは少なくとも伝統的な形態での商売に見切りをつけておられました。
そしてご自身の高校進学を機に廃業されました。
おじいさまは戦後の混乱で仕事の代金が回収できなかったり、
そもそも非常に過酷な仕事であったりと、少なくとも儲かる仕事ではなかったとおっしゃっていました。
戦前から戦後にかけての様子がよく分かる貴重なお話です。
阪本くんのおじいさまのお言葉にもあるように、
着物にまつわる思い出が必ずしも良いものばかりとは限りません。
しかし良い思い出でなくても、着物とそれにまつわる思い出を受け継ぐことは、
その人の人生に少しでも触れることができる貴重な機会になると思います。
いかがでしたでしょうか。
ぜひご自宅の着物に思いを巡らせていただけると幸いに思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
同志社大学社会学部1回生 松浦未空
![京ごふく ゑり善[創業天正12年]](https://www.erizen.co.jp/wordpress/wp-content/themes/erizen/img/common/logo_pc.png)